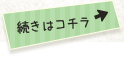受験から合格後の手続き記事一覧
宅建試験の実施概要
宅建試験は、財団法人・不動産適正取引推進機構が実施しているのですが、これには背景がありまして1987年までは各都道府県(知事)が実施していました。けれども、宅建業務というのは、実質的にパターン化された作業によって構成されており、裁量的な業務の余地が少ないということから、そのような資格を認可する業務をわざわざ自治体で行う必要がないという方針に至り、1986年の宅地建物取引業法の一部改正に伴って、先の財団法人へと民間委託されるはこびとなったのです。では、宅建試験の願書の配布や受験申請の受付や試験監督業務などもその不動産適正取引推進機構が担っているのかと言うと、実はそうではなく、これら試験の事務業務...
試験内容
宅建試験の内容というのは、何も毎年でたらめな範囲から提出されているわけではありません。その内容は、「宅地建物取引業法」の施行規則第8条によって、およそ次の7項目に指定されているのです。1つめは、「土地の形質・地積・地目・種別および建物の形質・構造・種別に関すること」。土地や建物の計測や区分についてですね。2つめは「土地および建物の権利や、その権利の変動に関する法令について」。土地や建物の権利関係についてです。3つめは「土地および建物についての法令上の制限に関すること」、4つめは「宅地および建物についての税に関する法令に関すること」、5つめは「宅地および建物の需給に関する法令と実務に関すること」...
受験手続き
宅建試験の申込は、郵送でもインターネットからでも行うことが出来ます。この際、希望の試験会場を指定できますが、先着順で割り振られますから、希望通りにいかない場合もあります。申請期間はインターネットの場合、例年7月の初旬から中旬まで。郵送の場合は7月いっぱいとなっています。宝くじを買っていない人が宝くじに当たらないように、申請を行っていない人は、試験を受けることができませんから、この7月という月に注意を払っておきましょうね。この宅建試験には受験手数料7,000円が必要になります。申請の際にはパスポートサイズの顔写真が必要になり、履歴書用のものではないので、注意しましょう。資格試験にありがちな光景と...
「登録」って?
宅建取引主任者の「登録」について、見ていきましょう。宅地建物取引主任者になるためには、宅建試験に合格する必要がありますが、実は宅建試験に合格した「だけ」では、主任者としての登録を行うことができません。実は1988年までは、宅建試験に合格さえすれば取引主任者としての登録をすることが出来たのですが、同年の宅地建物取引業法の改正によって、登録には「2年以上の実務経験」が必要になりました。ただ、この「実務経験」というのは、何も宅建試験に「合格してから」経験を積まなければならないということではありません。試験前に、すでに不動産に関わる実務経験を2年積んでいれば、宅建試験合格後に、ただちに取引主任者として...
実務経験に代わる講習
通常、宅地建物取引主任者登録の要件として必須の「2年の実務経験」の代わりになる「講習」について、説明しますね。宅地建物取引主任者の登録に際して通常必要になる「2年の実務経験」は、国土交通大臣が2年の実務経験を有する者と「同等の能力を有する」と認めたものについては、その実務経験の代わりになる、と宅地建物取引業法によって定められています。もちろん、国土交通大臣がその都度審査をするわけではなく、実態的には次のいずれかに該当することで、この代替条件を満たせることになります。ひとつは国土交通大臣指定の「講習」を修了すること。もうひとつは、国や自治体がその設立に関与する法人において宅地・建物の取引業務に2...
主任者証交付申請の前にも要講習
宅建試験に合格し、実務経験2年以上もしくはそれに代わる実務講習を受けたのち、いよいよ主任者交付申請を受けよう、というときに受けなければならない法定講習について、述べたいと思います。指定団体で実務経験に代わる実務講習を受けた人にとっては、「なにー!また講習かよー!」となる話でしょうが、宅地建物取引主任者の登録を行い、取引主任者証の交付を受ける際には、「交付申請前の6ヶ月以内」に、都道府県知事が指定する法定講習を受講する必要があります。この法定講習は、各都道府県に存在する公益法人や財団法人の、不動産適正取引推進機構の協力団体が実施しており、通常1年に4回程の頻度で実施されています。講習料は国土交通...